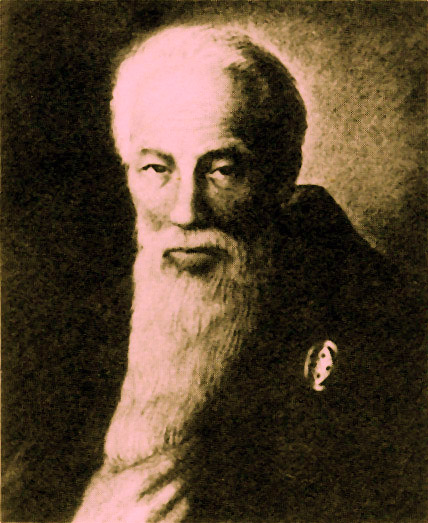
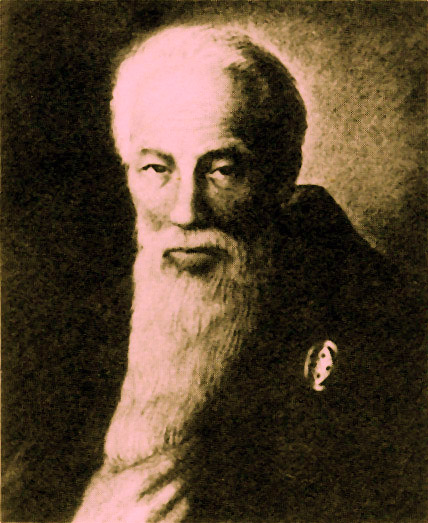 |
|
泉 谷 力 治
寺子屋の先生から 最初の小学校の先生に |
| 森嶽(しんがく)学校 |
|
明治5年(1872)8月、政府は「すべての国民は学校で教育をうけなければならない」というきまりを出しました。これを「学制発布(がくせいはっぷ)」といいます。 学制発布によって、子どもたちが学校でうけなければならない教育を、義務教育といっています。今は、小学校の6年間と中学校の3年間の9年間が、これに当ります。
このあと、8年に馬場目村の薫陶(くんとう)学校、内川村の湯又学校、9年に富津内村の環山(かんざん)学校・登美多学校・鶴湯学校、馬川村の高崎学校、大川村の大川学校、10年には馬場目村の中村学校がつくられました。 このあたりの村むらで、一番早いのが森嶽学校でしたが、最初は小池町の松浦三郎兵衛の家の、それまで開いていた寺子屋を学校にしました。その次の年には、古川町に学校がうつりました。そこは、泉谷力治が寺子屋を開いていたところで、それまでよりも広い校舎になりました。 しかし、ここも手ぜまになったので、10年(1877)には紀久栄町に新しく校舎を建ててうつりました。村の名前がついた五十目小学校に校名が変わったのは、明治15年でした。 五城目小学校だけでなく、他の小学校のはじまりも同じようなありさまで、お寺や神社、郷倉(ごうぐら)、村の大きな家などを使って、学校をはじめています。ですから、義務教育の最初の学校は、江戸時代からつづいていた寺子屋と、そんなに変わらないものでした。 |
| 泉谷寺子屋「愛顧堂(あいこどう)」 |
|
五城目小学校が、はじまりのころ2年ほど校舎にした泉谷力治の寺子屋は、五十目村と近くの村むらでは、最も大きな寺子屋でした。名前を愛顧堂といいました。また、森嶽塾、白水塾ともよんでいました。「白水」というのは泉谷の「泉」を上下に分解したものです。
それまで力治は、木材業を手広くいとなんでいる父泉谷庄八の家の一部をしきって、寺子屋を開き、子どもたちに教えていました。学制発布の時に、力治は寺子屋を止めましたが、新しくできる学校の先生になりたいと思っていました。 そのころ、五十目村には力治の愛顧堂と松浦三郎兵衛のほかに、荒川六郎兵衛、仙北屋、小笠原、近江屋の町の家や朱厳院、了賢寺、宗延寺のお寺で寺子屋を開いていたといわれています。このほかに、西野村の広幡政弥、下山内村の朝野竪磐、馬場目村の大森文八、中津又村の高泉清、浦横町村の小野太郎兵衛、野田村の加藤寛昭が寺子屋を開いて、村の子どもたちに教えていました。 寺子屋では、読書・習字・算術をおもに教えましたが、これを人びとは「読み・書き・そろばん」といっていました。 |
| 幼いころ |
|
泉谷力治は、天保5年(1834)9月5日、庄八の長男として生まれました。力治の生まれた前の年は「天保巳年のケカジ」と呼び名がつけられた、それまで例がないほどの大ききんでした。 そのため、悪い病気がはやったり、くらしに困った人びとが金持ちの家を打ちこわしたりすることが藩内の村むらにおこるなど、不安な世の中になっていました。泉谷家は、村でも指おりの物持ちといわれていましたから、生まれたときから力治は大事に育てられました。 特に、8人の兄弟のなかで、力治はただひとりの男の子どもだったので、あとつぎの子どもとして両親の愛を一身に集めました。 幼い力治が、学問好きなのに最初に気づいたのは、父の庄八でした。文字も読めない力治が、毎日のように朝のうちから父の部屋にやって来ては、漢字だらけの本をひろげるのです。 「おまえ、こんなにむずかしい本を読んでいるのか。」 と、父がたずねると、力治はこっくりとうなずきます。 「おもしろいか。」 「おもしろい。」 おうむ返しにこたえる力治の、つぶらなひとみが、きらきらひかっています。父は、もしかしたらこの子は学者になるかも知れない、と思いました。 |
| 学問にはげむ |
|
やがて、村の寺子屋に通うようになりましたが、「読み・書き・そろばん」という勉強は、力治にとってはたかが知れています。 父のもっている本を読んでは、いろいろ質問するようになしまいた。ふにおちないところがあれば、用事で家へやって来る藩の役人にたずねて、教えてもらうこともしばしばでした。 14歳のとき、父は近くの漢学の先生へ通わせます。力治は漢学に親しみ、特に伊藤仁斎(江戸寺最初期の儒者で京都の人。1627−1705)の『論語古義』『孟子古義』『童子問』を、よく読んでいました。また、『中庸』(かたよらない徳と、その道を説いた、中国の儒教の書。四書のひとつ)もよく勉強していました。 儒教(漢学の中の孔子(こうし)の教えで、四書などを学ぶ)という深い学問の世界に入りこんだ力治は、江戸で学びたいと思うようになり、安政5年(1854)20歳のとき親しい藩の武士が江戸に上るのについて行くことにしました。最後まで反対した父も、力治の熱意に負けて、 「1年で帰って来ると約束をしたら、江戸へ行ってよい。」 と、ゆるすしかありませんでした。 しかし、学問の奥まできわめようと決心している力治が、父との約束を守るはずはありません。4年、5年と江戸での生活が長くなってしまいました。6年目になると、家からの仕送りがとどかなくなりました。生活が苦しくなった力治は、北町奉行所にやとわれて、学問をつづけました。 学費を止めても、帰郷しないあとつぎ息子の力治を、文久元年(1861)夏、父は江戸まで迎えに行きました。54歳の父と27歳の力治は、いっしょに旅をして帰って来ました。 なつかしい森山が、少しも変わらずに迎えてくれたのに、力治はほっとしました。そして、ふるさとのために自分の学んだものを生かそうと思いました。 |
| 寺子屋を開く |
|
ふるさとで自分の学問を生かすには、地域の子どもたちに教えることしかありません。力治は、家の半分を仕切り、文久2年寺子屋を開きます。家業をつがせるのをあきらめた父が、力治の願いを聞いてくれたからでした。 この年、力治は村の医者落合貞玄の長女ミナと結婚しました。
ですから、江戸で学問を修めて帰った力治の寺子屋だというので、日ましに人びとの話題になりました。村の子どもばかりでなく、近くの村むらから通って来る者も多くなりました。村一番の寺子屋と呼ばれるようになりました。 ある時、論語の大事な一節を読み取れない弟子のために、いっしょにくり返しくり返し読み、昼食も食べませんでした。ようやく力治が満足ゆくように弟子が読めるようになったのは、もう夕方でした。その時、妻のミナも昼食をとりませんでした。それほど、力治は教育に熱心でした。 |
| 手伝い教員 |
|
学制発布によって、新しい時代の教育を感じとった力治は、寺子屋を止めて森嶽学校の先生になりました。五城目の人で、五城目にできた最初の小学校の最初の先生のひとりになったわけです。 ところが、力治は「手伝い教員」という身分で、正式の教員ではありませんでした。学問を修めた人なのに、漢学・儒教という古い時代の学問では、正教員と認めてもらえなかったのです。それでも、はじめての学校の名前が、自分の意見が通って森嶽学校となったのに、力治は満足していました。 そして、教育の仕事を自分の天職と考えていた力治は、給料も少ない手伝い教員を熱心につとめました。自分の寺子屋を学校に利用させていながら、手伝い教員によろこんでいるように見える力治の姿に、村の人びとは改めて真の教育者として力治を尊敬しました。 今、五城目小学校の校長室に、白いひげをのばした力治の写真と大きな書の額が、かけられています。「五城目教育の父」として、力治は昼も夜も五城目小学校にいるように見えます。 力治は、明治8年から五城目付近を治める第11小区の区長、11年から富津内方面の戸長を、県に命じられてつとめましたが、15年(1882)の五十目小学校と校名が変わった年に、ふたたび手伝い教員になっています。明治19年にむすこの順松が先生になると、力治は小学校の先生を止めて隠居の身になりました。 |
| その晩年 |
|
隠居はしても、力治に教えを願いに来る人は少なくありませんでした。そこで、新町の川岸近い所に小さな家を建て、漢学塾をはじめました。 塾では、漢詩や俳句も教え、たのまれるといくらでも書を書いてくれたといいます。長くのばしたあごひげの先の方を切って、自分で筆を作り、その筆で堂々とした文字を書いたそうです。
明治34年(1901)に妻に先立たれた力治は、42年(1909)12月5日、初雪の降った日に亡くなりました。76歳でした。 |
|
参考資料 『五小一世紀』(昭和49年 五城目小学校) |