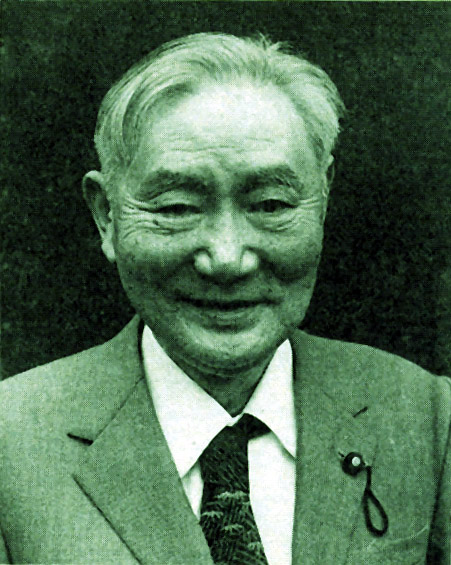
|
.
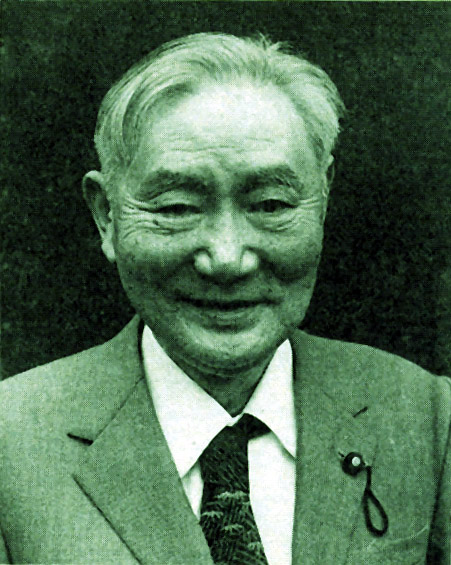 |
|
館 岡 栗 山
郷土の風景や行事を絵に |
| 絵馬をかく |
|
「豊治、おらさ、べらぼうかいてけれ。」 「うん。」 豊治は紙をひろげ、絵筆をにぎりました。きょうは、なん枚もたこ絵を仕上げましたが、たこ絵ではいいかせぎにはなりません。 そう思っていたところへ、 「絵馬かいてける豊治という人、あだだすか。」 といって、男が近づいて来ました。うなずいた豊治へ、男はとなり村からやって来たといいます。 「なんとか、すぐかいてもらいたいす。板は持って来たす。」 「どんな馬こ、かけばえすか。」 客の注文通りに、豊治はこれまでたくさんの絵馬を描いています。男もうわさを聞いて、たのみに来たのでしょう。絵馬はかい馬のために神様に納めるものですから、お礼がもらえるのです。たこ絵をかくより、ずっといいかせぎになります。えのぐも筆も買いたいと思っていたので、豊治は、一生けん命にかきました。 |
| 絵かきになりたい |
|
これは、日本画家館岡栗山(りつざん)10歳ころの話です。小さいときから絵のうまかった栗山は、友だちのたこ絵だけでなく、村の人びとからたのまれて絵馬を描いたりして、かせいでいたといいます。そのころから、栗山は絵かきになりたいと思っていました。絵をかくことが、本当に好きだったのです。
小学校を出て、明治44年に秋田師範学校講習科に入学し、15歳で五城目小学校の代用教員になりました。このまま学校につとめていたら、栗山は「絵の上手な先生」などといわれて一生をおわったかも知れません。しかし、「おれには、学校の先生はむかない。自由に好きな絵をかきたい。」といって、1年ばかりで先生をやめてしまったのです。 それから、師匠にもつかず、ひとりで絵の勉強にはげみました。けれども、独学では上達するのは困難です。 「東京さ、行かせてけれ。おれ、なんとしても絵かきになりたいす。」 「気でもくるったのか。絵かきになるなんて夢みたいなことばかりいって……。家を継いで、田さ出てまじめに働け。」 両親は、栗山のねがいを少しも聞こうとしません。 そんな家への不満から、町の落合病院の事務員になりました。ひまがあると画帳をふところから出して、季節の草花や花に寄って来る虫のようすを、ていねいにスケッチしている栗山を、落合医師はじっと見ていました。 あるとき、落合さんがいいました。 「館岡くん、絵かきになりたいのかね。それとも趣味で絵をかいているのかね。」 「先生、わたしは絵が好きで、絵かきになりたいと思っています。」 「そう思っているのだったら、ちゃんと師匠について勉強しないといけないよ。」 栗山は落合さんのことばに、うなだれてしまいました。わかっていることですが、これまでどうにもならなかったからです。 「君は見こみがある。努力したら、画家になれるだろう。応援をしてあげるよ。」 落合さんのことばは、目の前に明るい道が開けてくるように、栗山の胸にひびいて来ました。 |
| 修業時代 |
|
栗山が家出でもするみたいにして、絵の修行のために東京に出ていったのは、大正8年(1919)22歳のときです。弟子入りして絵の勉強するには、20歳ではおそいといわれていますが、栗山はかたい決心で上京したのです。 どんなにかたい決心も、病気にはかてません。半年ばかりで、帰らなければなりませんでした。でも、それにくじけず、郷里で健康を取りもどすと、栗山は25歳になっていましたが、ふたたび上京しました。 父は、決意のかたい栗山にあきらめて、止めようとはしませんでしたが、 「金は一文も送ってやれないからな。」 といいました。 栗山は、下絵かきなどのアルバイトをして生活費をかせぎ、勉強にはげみました。 そのころ、長春という号を栗山と改めています。高崎から見える森山が、クリのような形だったからだど、号の由来について話しています。きびしい修行、苦しい生活の中で、心にはいつも生まれ故郷があったのでしょう。 一人前の画家になってふる里に錦(にしき)をかざる自分の姿を想像し、自らをはげますために、故郷の森山を表す栗山という号を決めたのかも知れません。のちに、栗山はふる里秋田を描く日本画家になります。 |
| 院展初入選 |
|
大正15年(1926)、絵の勉強を深めるために、栗山は京都に移りました。洋画の勉強なら東京ですが、日本画の修行は京都の方がいいと思ったからです。京都での生活は、それまでよりずっと苦しくなりました。食うや食わずの日さえありました。 昭和3年(1928)有名な近藤浩一路先生の画塾に入ることができました。栗山は、30歳になってはじめてりっぱな師匠についたのです。
日本画家の場合は、院展に入選して絵かきの仲間とみとめられ、作品にも値段がつくようになりますが、絵が売れるわけではありません。栗山の苦しい生活はまだまだつづきます。 1回入選しただけでは、どうということはありません。連続入選すると、実力のある画家とされるのです。休むひまなく、栗山はは新しい画題を決めて、次に出品する絵に取組みました。 |
| 横山大観賞にかがやく |
|
夢中で絵をかく毎日を送っている栗山に、大へんな難問がつきつきけられました。師匠の近藤先生が日本美術院をはなれるというのです。そうなれば、弟子もいっしょにはなれるのが普通です。でも、栗山は院展の画家として、ようやく第一歩をふみ出したばかりです。 「苦しんで苦しんで考えたのですが、わたしは先生と行動を共にはできません。美術院に残ります。」 最初の志をつらぬいて、栗山は最後まで院展に出品しつづけました。 師匠を失った栗山は、血の出るような努力によって院展に連続入選をはたし、仲間たちをおどろかせました。そして昭和11年(1936)に、美術院研究会員となり、次の年の研究会展では「雨後」が横山大観賞となりました。それを機会に、安田靱彦(ゆきひこ)先生の教えを受けるようになりました。さらに、14年には院友となっています。栗山は、実力のある画家となったのです。 初入選以来、連続入選30回、43年(1968)には特待・無鑑査になりました。特待というのは、日本美術院院友の中でも、特別の待遇を受ける院友になったこと、無鑑査とは、これまで多く入選しているので院展に出品した作品は、監査をしないで展示されることをいいます。 |
| 郷里を描く |
|
戦争がおわる少し前の20年4月に、48歳の栗山は京都から五城目町に帰りました。よく年秋には、一日市町(今の八郎潟町)に移りました。
栗山は、いつも五城目市をスケッチしていましたが、市の人びとを描いた作品がたくさんあります。番楽・盆踊り・なまはげ・竿灯などの行事や芸能、森山・八郎潟・十和田湖などの風景が、栗山の絵の中で特に目を引く作品です。
短歌も若いころに五城目の歌人中村徳也と学んだことがあり、短歌会をつくっています。 秋田県内の展覧会の審査員をつとめたり、県内の日本画家の会をつくって勉強しあったり、湖東部のニュースを集めて新聞を発行したり、栗山の活躍は絵筆だけではないひろがりを持っていました。 昭和53年10月16日、81歳で亡くなりましたが、病床にあっても、「思いっきり大きい、踊りの絵をかきたい。何百人の群衆が踊っている、大きな大きな屏風絵をかいてみたい。」 といい、心は絵のことでいっぱいでした。 |
|
.参考資料 『栗山画談』9(昭和55年 秋田文化社)
|