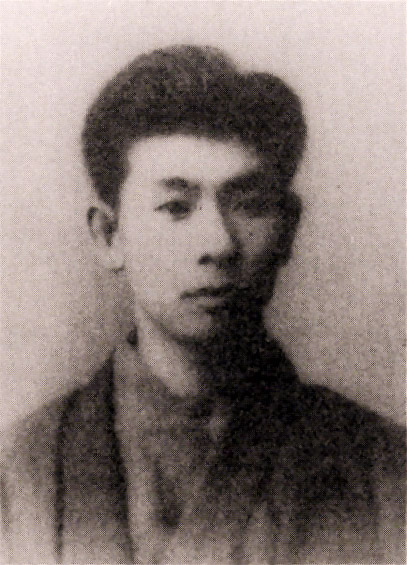
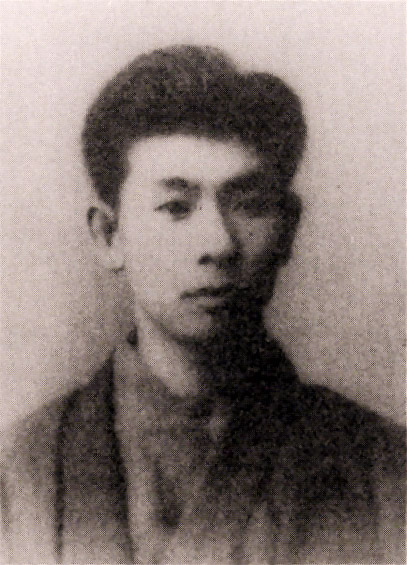 |
|
福 田 笑 迎
天才的画家 |
| 新しい時代の子 |
|
福田笑迎は明治2年(1869)10月18日、五十目村(五城目町)字上町202番地(小池町)の薬種商の家に生まれました。名前は貞助といいます。 父の勘助は町の旧家米田家から、あと取りのいない福田家に養子にむかえられた人でした。ですから、貞助は福田家の人びとが長い間待っていた男の子、総領だったのです。貞助は、家族や親せきみんなによろこばれて産声をあげたのでした。 貞助が生まれた明治2年といえば、つい1年前の9月に戊辰戦争がおわったばかりです。戦争のときは、幕府方の勢いがよく五城目にまで攻めこんで来るのではないかと、人びとはおびえたものでした。武士の世の中がおわって新しい時代がはじまりましたが、まだ社会はざわついていたのです。 それでも、時代の流れははげしく、4年(1871)には藩が廃されて秋田県になり、お金は厘・銭・円という新しい単位にかわりました。五十目村にも、7年(1874)に郵便局と小学校ができました。両方とも貞助の家の近くでした。こうしたことを見てくると、貞助は「文明開化」の申し子として、生まれて来たようにも思われるのです。 貞助の一生は、そのことを思わせるに十分です。 |
| ふしぎな小学生 |
|
すぐ近くの小学校に入学した貞助は、先生たちにとって困った子どもでした。 「貞助には、小学校の勉強はいらないなあ。」 困ったように先生はいいます。 「なにも教えることがないから、ほかの子どものじゃまにならないように、自由にさせたらどうだろう。」 「貞助のような子どもを、神童というのだろう。」 小学校で学ぶことよりも、貞助はずっと先の方を歩いていたのです。 家の土蔵には、それまで求めた江戸時代からの絵入り読みものの草双紙やさし絵のある小説の読本などが、たなにいっぱい積んでありました。 また、代々の福田家の主人たちが買い集めた、書や絵の掛け軸、絵巻、浮世絵なども、たくさんありました。 小学校入学前から、貞助は文化のつまっている薄暗い蔵の中で、すごい勉強をしていたのです。まず絵入りの草双紙を読むことをはじめました。読書は読本にすすみ、小学校をおえるころには、漢籍などのページをひらくほどになっていたのです。
「絵の道具がほしい。」 貞助がいうと、「どうして。」ともきかず、父は絵描きが使うような道具を、ひとそろい買ってくれます。両親にとっては、家の跡取りの貞助がかわいくてしかたありません。その息子が、勉強したい練習したいというと、その才能のゆたかなのに、ただただうれしくなってしまうのでした。 道具をもらった貞助は、毎日のように蔵の中にとじこもって、熱心に絵筆を動かしていました。 どれもこれも、およそ子どもらしくない知識や技能は、蔵での独学によるものでした。先生たちが困ってしまうのも、無理がありません。 いまも福田家には、貞助が子どものころに毎日練習で描いたという白描が、おしいれいっぱいに残っています。きびしい絵のけいこにはげんでいたことがわかります。 「神童」とよばれ、人びとが舌をまいた絵の才能は、人並みはずれた努力の結果だったのです。 |
| 子どもの画家 |
|
村の人びとは、10歳の貞助に絵を注文するようになりました。それに応じた作品には、瑞稲(ずいとう)とサインしています。貞助が12歳の明治14年(1881)秋、東北地方を御巡幸中の明治天皇が、秋田県をお通りになりました。このときから、号を笑迎と変えています。
しかし笑迎と号を変えたころには、手本からはなれ、笑迎独特の作品になりました。師匠にもつかずに、ひとりで自分の画風をつくり出したことは、おどろくしかありません。町内に保存されている絵は、人物を中心としたものが多く、笑迎の読書から得た歴史や物語の知識を生かした内容になっています。 笑迎の絵を見ると、これが10代の少年の筆から生み出されて作品とは、とても思えません。笑迎の天才を感じてしまいます。 |
| 上の学校へ |
|
家業をつがせるために、父は仕事をおぼえさせようと、小学校をおわったら秋田の薬種屋へ奉公に出すつもりでいました。そのころは、どんなお金持ちでも総領の息子は、家業をつぐ前に奉公に出るのが普通だったのです。 しかし一方では、息子の持っている豊かな才能や向学心を考え、他人のところで苦しい奉公をさせるのはかわいそうだ、と父は思うようにもなっていました。 「もっと勉強したい。だから上の学校にいきたい。絵の方も、もっとやってみたい。」 「そういったって、おまえは家の跡取りだよ。絵描きにはさせられない。」 「画家になる気はない、趣味でつづけるだけです。学校を出たら家に帰って来るから、ゆるしてください。」 父と子の意見がちがい、ことばのやり取りはありましたが、最後に父は笑迎のいい分を通してくれました。 希望通り、笑迎は秋田中学校(いまの秋田高校)にすすみました。中学生になっても、笑迎は絵筆をはなさず、細かな描写とはなやかな色彩の人目をうばう作品を生み出します。 ふすま絵やびょうぶ絵を好んで描きましたが、五城目町の指定文化財になっている「大江山図びょうぶ」や「中将姫図」「六歌仙図」などは、代表的な作品です。 |
| 政治家をめざす |
|
福沢諭吉の『学問ノススメ』を読んだ笑迎は、さらに東京へ出て慶應義塾(いまの慶應義塾大学)に学ぼうと決心します。その決心を、父はゆるすはずはありません。笑迎は、とうとう家出同様に上京しました。 慶應義塾で哲学を学んだ笑迎は、中江兆民の講義をうけ強く感じるものがありました。もう絵筆をとるといういとまはありません。時代は、自由民権運動がいっそう高まりを見せ、憲法の制定と国会の開設が間近にせまっていました。(憲法は明治22年に制定され、23年には第1回衆議院総選挙が行われました)中江兆民は、政治運動の中心人物のひとりでした。 笑迎は政治家になろうと思いました。家業をつぐわけにはいきません。家業は妹についでもらうことにしました。 東京で新聞記者をしながら、笑迎は政治家を目指して活動をつづけ、次第に人びとの注目を集めるようになります。 政治家の第一歩は国会議員になることです。笑迎は東京でよりも生まれ故郷で選挙にうって出ようと考え、明治23年(1890)22歳になった笑迎は、秋田に帰りました。そして、自分の政治上の考えを、県民に知ってもらうのは新聞によるのが一番と思い、明治29年(1896)仲間と「秋田新聞」を発行します。この年、五十目村は五城目町となっています。 しかし近代化のおくれていた秋田では、笑迎の新しい政治の考えは、選挙民に理解されなかったようです。衆議院の選挙では、わずかの差で当選できませんでした。 |
| 早い死 |
|
失意のうちに、明治39年(1906)笑迎はふたたび東京に出ました。
政治活動のあわただしさに忘れていた、笑迎の絵心がよみがえったのです。また、故郷のこともなつかしく心に浮かんで来ます。それが、『評伝四ツ車大八』を書かせます。 ようやく本来の自分を取りもどしたとき、もう笑迎の持つ時間は残り少なくなっていました。明治42年(1909)10月16日、40歳の若さで笑迎は亡くなりました。 あふれるほどの才能を、生かしきれずに他界したのは、まことにおしいといわずにいられません。家業をつぎながら、その画業をさらにのばすことが出来たなら、と思ってしまいます。画家として活躍したのは、10代の10年間でした。早熟の天才というべき人でした。 |
|
参考資料 『人・その思想と生涯 福田笑迎』小野一二(昭和49年「あきた」9月号 秋田県広報協会)
|